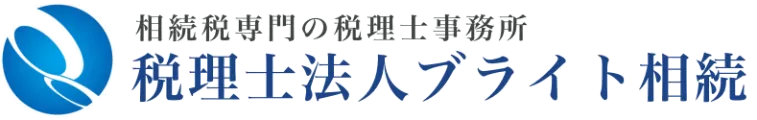相続税の配偶者控除の使い方
配偶者控除によって、1.6億円までは相続税はかかりません。ただし、相続税の節税だけではなく、残された配偶者の老後の生活資金の確保が何よりも大事です。
このページの内容はYouTubeでも解説していますので、まずは動画を見てざっと理解していただいてから読んでいただくとより理解が深まると思います。
相続税を1番安くする配偶者控除の使い方
配偶者控除を1次相続で使いきると1次相続の相続税は大幅に安くなります。
ただし、配偶者に多くの遺産が相続されるため、次の2次相続の相続税が高くなってしまいます。
そのため、1次相続で配偶者控除を使い切らない方が2次相続まで含めたご家族トータルでの相続税は安くなります。
ただ、相続税の負担だけを考えて配偶者控除をいくら使うか決めてしまうと、配偶者の老後の生活に支障をきたすことがあります。
老後の生活を考えた配偶者控除の使い方
相続税が一番安くなるという理由で、配偶者に必要な財産が相続されず、老後の生活資金が足りなくなることがあります。
2次相続のシミュレーションをお願いされて、ご長男の方と話す中で、お母さまの生活資金にあまり余裕がない相続プランを作られる方が多いんですね。
例えば、目黒区の老人ホームの費用相場ですが、入居一時金で平均1,000万円を超えて、月額利用料も30万円を超えていることをご存知ですか?
誰にでも、将来の医療費負担だったり、老人ホームへの入居だったりが起きる可能性は十分にあります。
配偶者が必要な遺産を相続していないと、十分な医療が受けられなかったり、老人ホームに入れない、なんてことが起きてしまうんですね。
相続によって新たに発生する費用もある
不動産を相続した場合には、固定資産税を支払うことになったり、マンション管理費を支払うことになったり、新たな支出が発生することもきちんと考えておく必要があります。
つまり、配偶者のご年齢や生活水準、新たに発生するであろう支出を考えて、余裕を持った相続プランにし、配偶者控除の額を決める必要があります。
過度な節税よりも、必要な財産を相続によって確保することを優先して考える必要があると思っています。
不動産を相続しないで大変な目に遭うことも...
節税目的で不動産を配偶者の方が全く取得しなかった場合、長男の妻と折り合いがつかずに自宅を出ていく、または追い出されることになることもあり得ます。
慣れ親しんだ自宅を出ていくことになった場合には、歳をとってから賃貸物件を探すことになり、縁もゆかりもない土地に賃貸暮らしをするなんてことも起こりえてしまいます。
こんなことにならないように、不動産を取得した方がいいというケースもあるんですね。
相続が発生し配偶者控除を使われる方へ
相続が発生した方のご相談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。