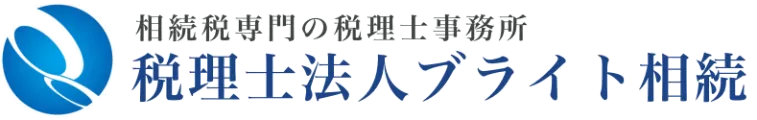亡くなる直前に引き出した親の預金の税務署に指摘されない相続税申告方法
入院費用、老人ホームの費用、葬儀費用など、亡くなる直前に親の預金を引き出すことは通常よくあります。しかし、相続税申告時に正しく処理しないと税務調査の対象になり、罰金(追徴税額)が発生することになります。
このページの内容はYouTubeでも解説していますので、まずは動画を見てざっと理解していただいてから読んでいただくとより理解が深まると思います。
税務署に指摘されない預金引き出しの相続税申告方法
最新の税務調査においても、申告漏れ相続財産の金額としては、現金・預貯金等が最も多くなっています。税務署に指摘されない預金引き出しの相続税申告方法を解説していきます。
よくある直前引き出しと使用の例
- 入院費用の精算
- 葬儀費用
- 老人ホームの費用精算
- 自宅の修繕費
- マンション管理費
- 水道光熱費
- 相続人の口座へ振替
- 手元現金として保管
一番多いのは入院費用の精算ですが、これらをどのように処理して相続税申告すべきかが問題になります。
特に、ご本人が預金の管理をしておらず、ご長男様が管理して生活費をそこから引き出しているような場合には引き出し金額や頻度が多いケースもありますので要注意です。
税務署に指摘されない預金引き出しの処理方法
時系列で預金引き出しを見ていきましょう。

相続税の財産評価は、亡くなった日時点の相続財産を評価するのが基本です。したっがって、手元現金として計上すべき金額は、引き出した預金から、生前に支払った入院費用を差し引いた金額になります。
なお、葬儀費用は債務として計上し、相続財産から引くことができます。
使った金額を処理する際の留意点
使った金額は、
原則:証票ベースで金額を算定する
例外:証票がない場合は、前月の実績から推定する
証票がない場合は、税務署に説明できる範囲で計上することになります。
具体的な処理手順

通帳の赤線ラインが亡くなったタイミングで、亡くなる直前の預金の引き出しをピックアップします。A銀行・B銀行・C銀行のように複数の金融機関とお取引がある場合は、金融機関に関係なく時系列で預金の引き出しを並べ替えし、大きな取引については1つ1つ確認していくことになります。
まとめ
・税務署は直前の預金引き出しを必ずチェックしている
・直前の預金引き出しは正しく財産計上しないと税務調査の対象になる
・直前の預金引き出しは正しく処理して申告すれば問題はない
・勝手な使い込みは遺産分割のトラブルになることもある
預金の引き出しが税務署にバレて税務調査の対象になる理由
預金を引き出したらどのように処理すれば良いかはおわかりいただけたと思いますが、なぜ税務署にバレるのかを解説していきたいと思います。
税務署の税務調査の体制

品川税務署の資産課税課は1割程度の12名となっていて、少数精鋭の部隊となっています。
pipitLink

pipitLinkの導入によって税務調査の効率性は著しく向上しています。
税務調査で追徴課税となる場合の罰則
追徴課税の種類
延滞税:~約9%(年利)
法定納期限を過ぎた場合、法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については原則として年7.3%、それ以降は14.6%となっています。
過少申告加算税:~約15%
過少申告加算税は、期限内申告書を提出した者が、税務署の調査を受けた後に修正申告を提出した場合や税務署から更正処分を受けたりした場合に課させる税額のことです。
無申告加算税:~約20%
無申告加算税は、期限後申告書を提出した者、税務署から課税価格の決定を受けた場合に課させる税額のことです。
重加算税:~約40%
重加算税は、課税価格又は税額等の基礎となるべき事実の全部もしくは一部を隠蔽し又は仮装していた場合に課される税額のことです。
税務調査が行われた際に、「預金を引き出してると思いましたが何に使いましたか?」と質問され、「葬儀費用で使いましたからもうありませんよ」と回答した場合、預金の引き出しを認識しており、意図的に隠したのではないかと疑義を抱かれ重加算税が課されるリスクがあります。
直前引き出し1,000万円が漏れていた場合の罰金
相続財産の金額ごとに、重加算税が課された場合の罰金を計算してみると以下の通りとなります。
| 相続財産 | 相続税 | 重加算税(40%) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 100万円 | 40万円 | 140万円 |
| 1億円 | 150万円 | 60万円 | 210万円 |
| 2億円 | 300万円 | 120万円 | 420万円 |
配偶者がばれた場合のリスク
配偶者が相続する場合、1.6億円までは相続税が課されないから大丈夫ですか?と聞かれることがありますが、そんなことはありません。
むしろ、悪意ありと見做された場合、配偶者控除が適用できず、相続税が多額に発生し、さらに重加算税が課させるリスクがありますので、むしろきちんと処理して相続税の申告を行う必要があります。
相続税申告はお任せ下さい
豊富な実務経験とノウハウにより、スムーズかつ無駄のない手続きで、高品質で低価格な相続税申告をご提供します。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。